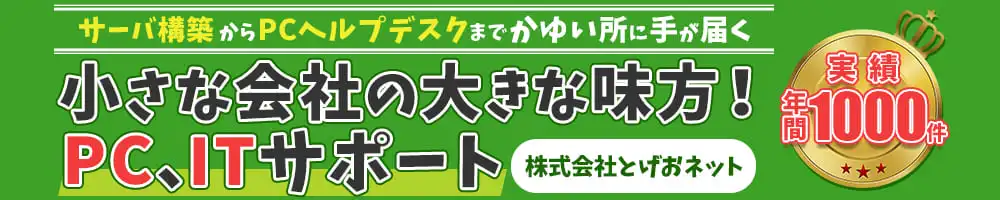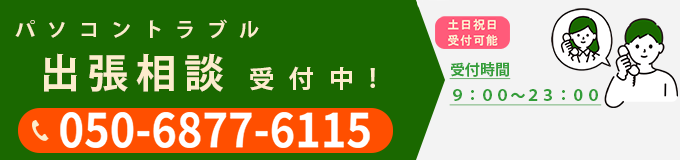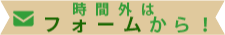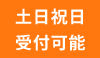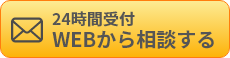2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法により、企業のペーパーレス化を促す仕組み導入や電子での帳票管理のハードルが下がりました。従来では電子データを基にした帳票であっても紙に出力して物理的なファイリングをするといった手間を行っていましたが、適切な要件を満たすことで、電子データの帳票をわざわざ紙でファイリングする必要はなくなり、物理的な管理や人の手間を大きく軽減できます。
施行から2年間(2022年1月~2023年12月)は、移行期間として、従来のように紙管理を継続することも可能でしたが、2024年1月から猶予が終わり「紙管理ではダメ」なパターンも発生します。この2年間で企業は改正電子帳簿保存法に適した仕組みを構築しなければならないということになります。
あらためて、2022年改正電子帳簿保存法は何を目的としていたかを整理し、どのような対応をすべきかを取りまとめました。改正電子帳簿保存法への取り組みがまだの方はもちろん、すでに取り組みができている方も、改めて対応を見直し、改善点がないかどうかの点検にもご活用いただければ幸いです。
具体的なソリューションについては別ページにまとめましたので以下のページもあわせてご参考ください。
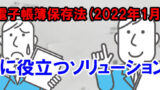
・記載の記事は2023年10月時点の情報となります。必ず国税庁(所管省庁)や経済産業省・財務省、各地方自治体で公表されている最新情報をご確認ください。
↓PCトラブルなど社内IT環境にお困りなら↓
2022年改正電子帳簿保存法のおさらい
改正電子帳簿保存法については、国税庁がわかりやすくまとめた資料を公開していますので、詳細はこちらの資料をご確認ください。
そのなかで、特にシステム担当者として留意すべき点を簡単にまとめます。
電子帳簿保存法の保存区分
電子帳簿保存法では、以下の保存区分を示しています。
①電子帳簿等保存
会計ソフトの登録や、デジタルで作成された国税関係書類(e-TAXデータなど)の電子データ保存。オンプレミスの会計ソフトであれば独自の拡張子で保存されたり、データベースシステムに保存されるデータもあります。データをシステム上に蓄積した後、正規の帳票として完成させた場合はPDF形式など一般的なファイル形式で出力できる場合もあります。
また、取引先から請求書等を受領する場合に、従来は郵送で印刷された紙を保存していたかもしれませんが、電子メールでPDFファイルでもらう場合や、ExcelファイルやWordファイルでもらう場合、さらには電子メールの文面そのものが請求フォーマットとなる場合もあるかもしれません。これらは【要件を満たしていれば】紙に印刷することなく、電子データとして保存しても帳票としての効力を発揮できるようになります。
なお、区分:①電子帳簿等保存は2022年改正時点では、紙管理を維持してもOKです(選択は任意)。
②スキャナ保存
従来通り郵送などにより紙で受領した書類を、スキャナやカメラ機能で取り込むことで電子的に保存する方法です。
なお、区分:②スキャナ保存は2022年改正時点では、従来通り紙管理を維持してもOKです(選択は任意)。
③電子取引(注意が必要!)
オンライン上の取引をしたことでネット上で随時帳票を生成できる方法。例えばオンラインで物品を発注した場合の請求書は、現在多くの場合インターネットのwebサイト上でダウンロードできます。取引先によってはweb請求書システムで請求書を発行しており、そのサイトからダウンロードして対応している場合も増えているのではないでしょうか。
2023年12月までは経過措置として従来通りの運用(=電子データを印刷して紙の保存)でも可能ですが、2024年1月から、区分:③電子取引については、データの保存が必要となり、電子取引データを紙に出力し保存しても効力を持たなくなります。
最低限の保存要件
もちろん、ただ帳票を電子データとして保存していればよい、というわけではなく、電子保存のためのいくつかの要件があります。まずは最低限の要件から。
・システム関係書類等を備え付けること
要は、マニュアルが用意されていることです。
システムを導入すれば当然そのシステムに類するマニュアルや説明書があるはずですので特段の用意は不要です。しいて言えば、必要な時に正確な情報がすぐ参照できる状態であることが、本来の目的です。
・保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
極端な話、電子化しているのに参照するためのパソコンがない、表示するためのディスプレイがない、印刷できるプリンターがない、といったことは当然ながらNGです。
可能性があるとすると、自社開発のシステムなどの場合で、必要な帳票がエラーとなって適切に出力ができないとか、帳票出力の内容に整合性や再現性がないなどが起こってはいけません。
タイムスタンプ要件
帳票が改ざんされていないかどうかのチェックとして「タイムスタンプ要件」があります。以前はタイムスタンプを厳格にするための厳しい要件がありましたが、改正後は「電子データを受け取って約2か月と7営業日以内」であれば有効な帳票となります。自署も不要です。
また、訂正や削除といった変更履歴が記録できるシステム上で管理できれば、タイムスタンプ要件自体不要となります。例えば電子帳簿保存法に適合したクラウドサービスを使えば、自社でタイムスタンプ要件を考慮する必要はなくなります。
検索要件
紙保存をしていた際には、いつ、何の種類の帳票がどこにファイリングしているかを管理していたと思いますが、電子データの保存についても同様です。何らかのデータで保存したものの、それがいつ何の帳票かが判断できない状態で保存されていては要件を満たしません。
これも以前はかなり厳格に定められていましたが、改正後は「取引金額」「取引年月日」「取引先」で検索できれば要件を満たします。
また、要件には「税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようになっていること」であれば、検索要件は不要としています。
通常、高度な検索機能を持つ会計システム・情報システムでは取引年月日や取引先などを紐づけて利用します。しかし、これらのシステムを整備するとなるとかなりの投資が必要になるのは事実です。
「必要なデータは、必要となったタイミングで直ちに用意できる(人の手を介して探せば取り出せる)」を満たせばよいというわけです。紙管理の頃も、どの年の何の資料がどこに保管するかは各社の運用ルールがあり、それが税法上のルールとして明確に決まっているわけではありません。目的は【適切な帳票をすぐ参照できるための整理整頓】です。電子保存でも紙管理の時と同じように目的が達成できればよいということです。
もちろん、誰でも簡単かつ明瞭に検索し適切な結果を得られるシステムがあることが理想ですが、改正法ではそこまでの厳格さを求めておらず、それよりもペーパーレス化の推進を重視しているといえます。
↓PCトラブルなど社内IT環境にお困りなら↓
具体的な改正電子帳簿保存法への対応
ここまでは実際に国税庁などから発信された概略をまとめたものですが、一企業のシステム担当者への目線でもう少し具体化していきます。
本件の大部分は、現時点はシステム化というよりも、自社の経理部門の運用方針に絡むものです。まずは、経理部門が電子帳簿保存法に対してどのように対処しようと考えているかをヒアリングしましょう。選択肢としては大きく以下のようなものが考えられます。
運用は変えない(電子化対応は消極)
ペーパーレスや電子化のメリットは非常に大きいはずですが、総合的に判断した結果、改正電子帳簿保存法には適合せず現状の運用を変えない、という判断もあるかもしれません。ただし、リスクもしっかり踏まえたうえでの判断が望ましいです。
改正電子帳簿保存法では、今までのどおり運用するにしても、注意しなければならないポイントがあります。
区分「電子取引」の帳票を紙出力したものは2024年1月以降税法上の効力を持たない
取引先がオンライン取引でインターネットや専用システム上で直接請求書を発行している場合、旧来の方法ではそれをプリンターで紙出力して保存していたかもしれませんが、これは2024年1月からは無効で、紙ではなくデジタルデータのほうが正となります。
オンライン取引でも、特定のwebサービスやシステムからの出力ではなく、メールやストレージサイトなどを経由して提出される単体ファイルであれば「電子帳簿等保存」の区分のため旧来の紙出力→保管は任意選択で可能としています。
ただし「なぜ紙保存を維持したいか?」を確認するのは、法改正のこのタイミングとしてはよい機会かもしれません。
電子帳簿に対応した場合過少申告加算税が軽減される
何らかの申請ミスというのは人の作業なので発生する可能性は否めません。一定の電子帳簿対応ができている場合、過少申告加算税が軽減される(通常10%→5%)場合があります。
ある程度適切に電子帳簿への対応をシステム化していれば、システム上で適切なチェック機構を持つ場合がほとんどなので、そもそも人為的なミスを軽減できる可能性もあります。
事業を続けていけば、必然と取り扱う帳票は増え続けます。年々圧迫するのは、物理スペースと紙という物体を取り扱うというコスト(手間)です。法改正は、自社の運用や手続きを見直す絶好の(あるいは唯一の)機会です。今の運用が最善最適なのかどうかをぜひ見直してもらいましょう。
適合するクラウドサービスに移行する
改正電子帳簿保存法に適合したクラウドサービスを利用することは、もっともスムーズな手段です。今の時代は普通のインターネットブラウザさえあれば自社で巨大なサーバを抱える必要なく高度なサービスを受けることができます。
特に国税にかかわる経理業務をクラウド化することができれば、電子帳簿保存法にほぼ適合することができます。電子化に手間のかかる経費精算、請求書などに特化したクラウドサービスもあります。
これらのサービスに移行するためには、経理業務の運用手順変更だけではなく、内部統制やその会社の税理士事務所などとの連携も必要となる場合があるため、システム担当者で積極的に対応することは難しい場合が多いです。
ただし、このようなクラウドサービスを経理部門が導入すると、逆に自社側での設備投資はほとんど発生しません。コストは純粋なシステム利用料だけとなります。
強いて考慮すべき点があるとすれば、アカウントを適切に管理しているか(アカウントを使いまわししていないか、異動・退職者のアカウントを放置していないか)、セキュリティは適切に対策されているか(クライアント証明書やグローバルIP制限など、セキュリティを向上できる機能がサービスを活用しているかどうか)をシステム管理者としてチェックしておくなどです。
現行のルールを維持しつつ電子化に適合する(要注意)
「紙管理は減らしたい、でも専用のシステムを導入するほど大きな対応もできない」となると、現在の仕組みの中で工夫をすることとなります。この場合には、システム管理者としていくつかの備えを考える必要があります。
代表的な点を示します。
障害に耐えられるファイルサーバ、NASの用意
電子帳簿保存法にデータを保存する機器要件を具体的に示しているわけではないですが、当然ながら保存義務のある帳票が喪失したり、適切にアクセスできない状態になってはいけません。一方で、データを保存するストレージは一般的には寿命がありますし、機械ですのである日突然故障することがありえます。
経営者や経理担当者は、電子保存のリスクに機器故障由来のデータ喪失を懸念していますので、耐障害の設計・機能を含んだ機器への移行・導入を検討しましょう。
ファイルサーバ・NASの(物理的に異なる場所への)バックアップ
物理的に異なる機器にバックアップを取ることも重要となります。
耐障害の機器とはいえ、すべての障害に耐えられるわけではありません。地震等災害による転倒・火災といった被害や落雷による機器ショートなど、機器単体で防げない事故が起こる可能性はゼロではありません。また、ランサムウェアやマルウェアなどによるファイルの破壊も脅威です。
これらの対策には様々なアプローチがありますが、シンプルなのは「物理的に異なる場所へのバックアップ」です。狭義では異なる機器を意味しますが、理想的には物理的に異なる場所への保存です。
物理的に異なる拠点を確保することは、以前であればデータセンターと契約するなど、ハードルが高かったですが、現在はクラウドストレージサービスを活用するといった方法もあります。
ファイルサーバ・NASの空き容量に注意し、定期的にチェックする
これまで紙で管理していた帳票を電子化するにあたって、多くはスキャナでの画像取り込みによりPDFや画像ファイルとして保存されます。これらは通常のオフィス系ファイルよりも大きいものになります。
年間でどれだけの帳票を電子化するかにもよりますが、電子化に当たりファイルサーバ容量が急激にひっ迫する可能性があります。ファイルサーバの空き容量や消費量には十分注意し定期的に監視をしましょう。
電子帳簿保存においては、カラーであるかどうかは要件ではなく、必要な情報さえわかればモノクロでも問題ありません。スキャン設定が必要以上に高解像度過ぎて容量をひっ迫しないように、スキャナのデフォルト保存設定(カラー/モノクロや、解像度等)も検討しましょう。
Windowsサーバを使っている場合はVSSを活用(ソフトウェアバックアップ)
紙を廃棄する場合は、シュレッダーするなど明確な破棄の意思が必要です。しかし電子データは手軽に削除できてしまうため、機器障害などとは別に、人為的な(悪意のあるなしにかかわらず)データの喪失というリスクにも備える必要があります。
バックアップ先に常に増分だけ取得していくという方法は、安全ではありますが実用的ではありません。バックアップの仕組みによっては削除データは「ゴミ箱」的な領域に保存するケースもありますが、容量を圧迫します。
対処の一つとして、ファイルサーバがWindowsサーバの場合、VSS(ボリューム車道コピーサービス)という機能を使うことができます。VSSは一定期間でスナップショットを保存することで、その日時点のファイルを復元することが可能な機能です。誤削除などから復旧したい場合には非常に便利な機能です。
↓PCトラブルなど社内IT環境にお困りなら↓
どうしても上手くいかない時は
インターネットで検索して色々な方法を試してみたけどうまくいかない…
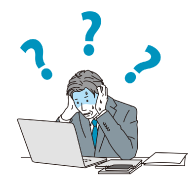
とげおネットまで
お気軽にご相談ください!!
電話・メールフォームから
お問い合わせください!
▼ ▼ ▼
とげおネットでは
出張サポートにて
お力になれます!
インターネットで検索して色々な方法を試してみたけど上手くいかない場合はとげおネットまでお気軽にご相談ください。出張サポートにてお力になることが可能です。
まとめ
いかがだったでしょうか?改正電子帳簿保存法について、システム担当者で留意すべきポイントをまとめました。
本文中でも記載しましたが、改正電子帳簿保存法への対応にはある程度の柔軟性もあり、会社がどのような方針を取るかの判断が必要となります。関係各所へヒアリングを実施し、自社で適切な運用となるよう、経理担当者をサポートしてあげましょう。
改正電子帳簿保存法に取り組むにあたってのシステム的なご相談、ファイルサーバやNASの導入やバックアップソリューションでお悩みの場合は、ぜひとげおネットまでお気軽にご相談ください。